
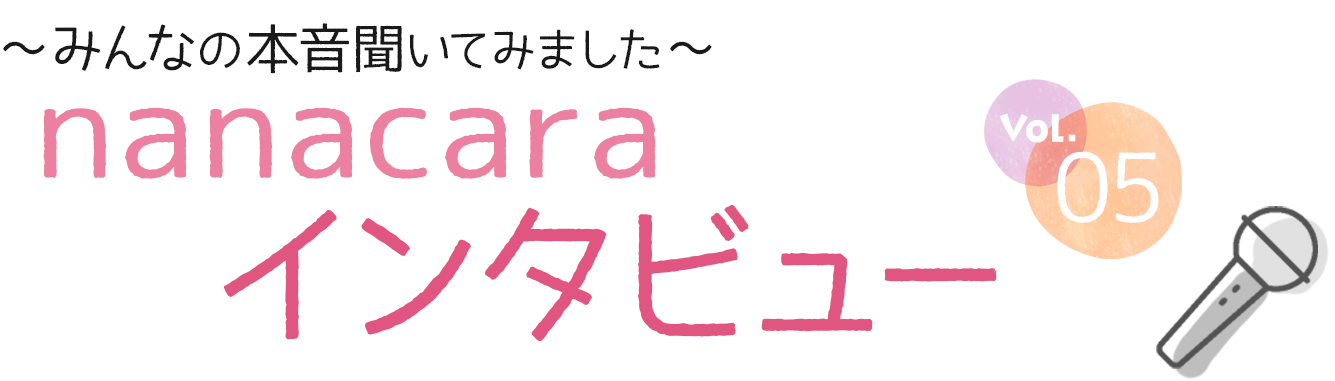
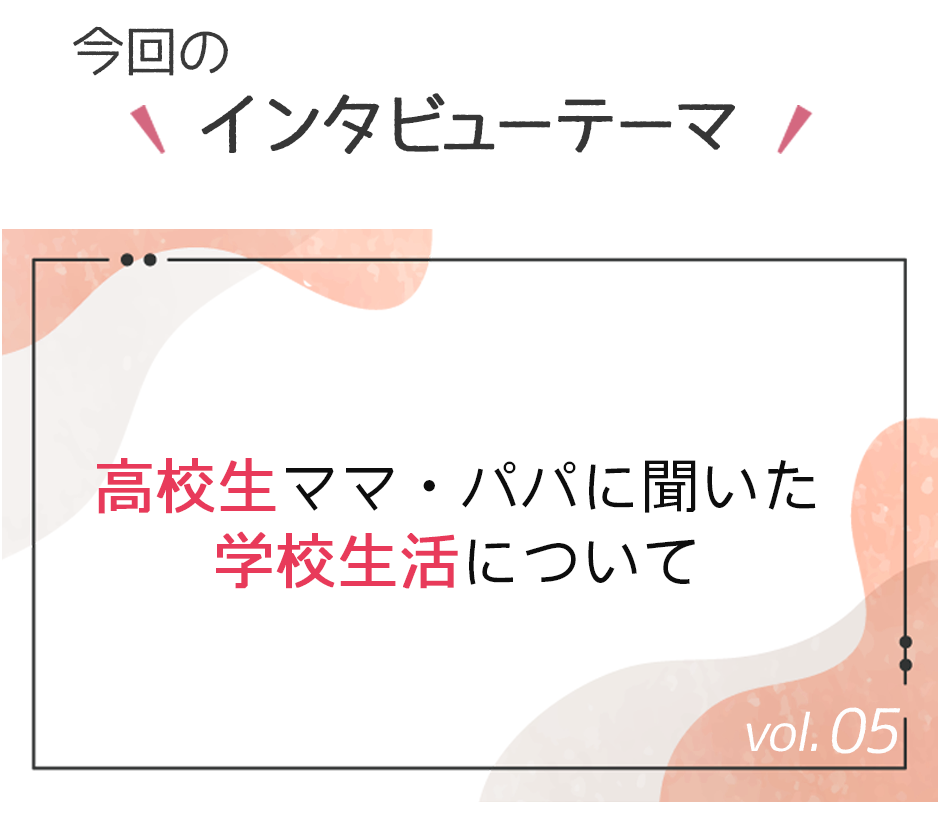
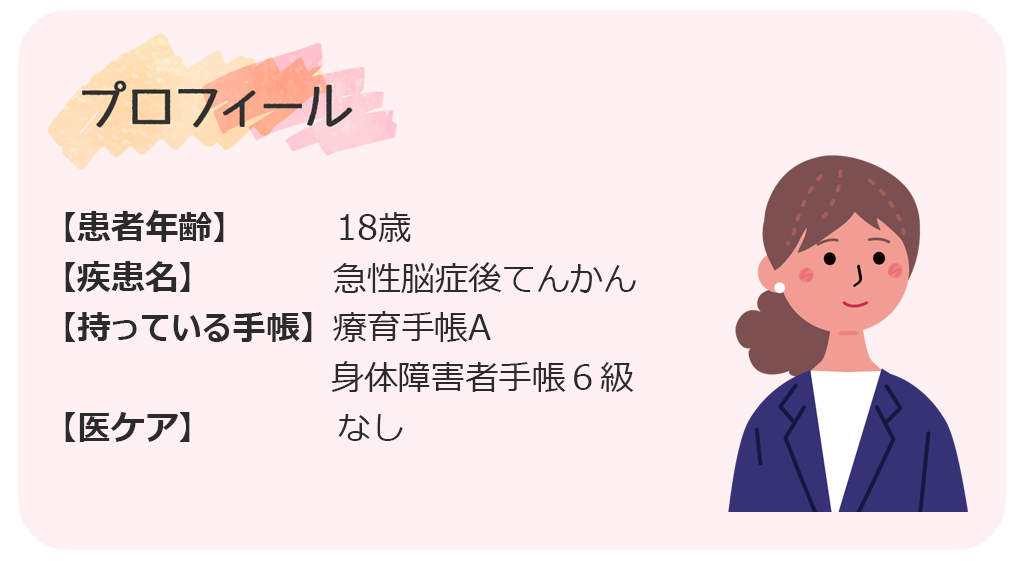
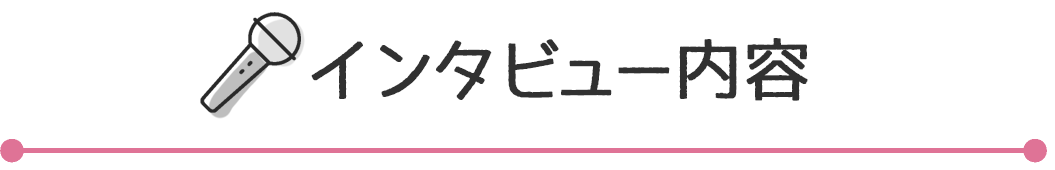
小学校の頃は、読み書きができたらいいなと思っていましたが、今は無理にさせると発作にもつながるので、無理はさせないようにしています。
自分の名前を中途半端に書けると、何かにサインをしてしまって怖いなという気持ちもありました。
人を選ばず、周りの人とにこやかに過ごせればそれで十分かなと思うようになりました。
中学校では、スクールバスのお迎え時間が私の仕事の時間ギリギリになることがあり、早めに迎えに来てほしいと何度もお願いしましたが、結局あきらめました。
乗り物が好きな息子は、車で送るとそれに味を占めてしまうのではないかと思い、絶対にスクールバスに乗せたかったんです。
...続きを読む
日々の生活に追われて、子育てがいっぱいいっぱいになってしまっていました。
今振り返ると、仕事のことよりももっと息子に構ってあげればよかったなと思います。

小学校の時は、連絡帳にも書いていましたが、朝会ったときに直接先生に伝えるようにしていました。
連絡帳は夜に記入するので、その日の朝にあったことは朝のうちに口頭で伝えていました。
例えば、「鼻水が出ています」「咳をしています」「機嫌が悪いです」といったことですね。
中学校・高校では、基本的に毎日、紙の連絡帳でやり取りをしています。
日々の情報共有として、「今日は調子が良い」など、その日の様子を書いています。
本人は自分の意見を話せないので、なるべく知ってもらいたいことを細かく記載しています。
特別なことがある時は、先生から電話で連絡が来ることもあります。例えば、発作が多かったときなどです。
...続きを読む
息子の発作は短いので、先生には見守りながらしっかり情報を共有してほしいと思っています。
発作のあとには眠たくなることが多いので、その時はゆっくり休ませてあげてほしいです。
このことは、年度が変わるたびに必ず先生に伝えています。
中学校の先生やデイサービスの先生は、私の要望に応えてくださり、発作の情報をまめに資料にまとめてくださっていました。
また、知的障害もあるため、どこでやる気のスイッチが切れてしまうかわからず、突然「学校に行きたくない」と言い出すこともあります。
だからこそ、学校やデイサービスは楽しい場所であってほしくて、無理強いしたり強要したりはしてほしくないんです。
以前、ロタウイルスワクチンの取材を受けた際に作った自己紹介の冊子があるので、それも活用して息子のことを周りに理解してもらうように情報共有をしています。
...続きを読む
今は緊急薬の処方はありません。
小さい頃には処方されたこともありましたが、実際に使ったことはありません。

今は抗てんかん発作薬を3種類服用していますが、過去もだいたい3〜4種類を常に飲んでいました。
保育園から小学校低学年の頃、副作用で食欲がすごく落ちてしまって、ご飯や牛乳など白いものが食べられませんでした。
また、熱が体にこもってしまい、体が熱くなることもありました。
そんな時は、ポテトや芋、卵かけご飯など、食べられるものを工夫して炭水化物を摂らせていました。
保育園にはアイスノンや保冷剤を預けて、脇に保冷剤を入れられるようなベストも作って熱を下げる工夫をしていました。
小学校では冷房の効く部屋で休憩させてもらうこともありました。
...続きを読む

小学校では、医師からの許可書を提出してプールに入っていました。
帽子の色を変え、特別支援学級の先生がそばでしっかりサポートしてくれていました。
体育や運動会では、麻痺があるため無理のない範囲で取り組み、リレーではハンデをもらって走ることもありました。
修学旅行も行きました。
中学校・高校では、プールの際に先生が付き添い、環境が変わることで寝つきが悪く疲れてしまうこともあったものの、修学旅行にも参加しました。
運動会も元気に参加していました。
...続きを読む

小学校は地域の学校の特別支援学級に通っていました。
見学に行った特別支援学校は家から遠く、何かあった時にすぐに迎えに行けないと思ったことが大きな理由です。
それから、1歳の頃から同じクラスで過ごしている保育園の友達がとてもよくお世話をしてくれていて、この子たちと一緒なら大丈夫かもしれない、と安心感もありました。
息子はほとんど支援学級のクラスで過ごしていて、通常学級には朝の会や終わりの会、給食の時間に参加していました。
通常クラスで授業を受けるときは、支援学級の先生がいつもそばについてサポートしてくれていました。
毎朝、私が一緒に歩いて登校し、放課後は校内の学童に1~2年生まで参加していました。
中学校になると、できることとできないことの差が大きくなりすぎて、地域の学校では先生のサポートが十分に受けられないだろうと感じ、支援学校への進学を決めました。
小学校の支援学級の保護者とも話す中で、息子の障がいの度合いから支援学校が適していると感じていましたし、同じ支援学校に通う一つ上の知り合いもいて安心感がありました。
高校は中学校と同じ支援学校へ進学しています。
何より、「どれくらいきちんと見守ってもらえるか」という点を選ぶ際に大切にしていました。
...続きを読む