
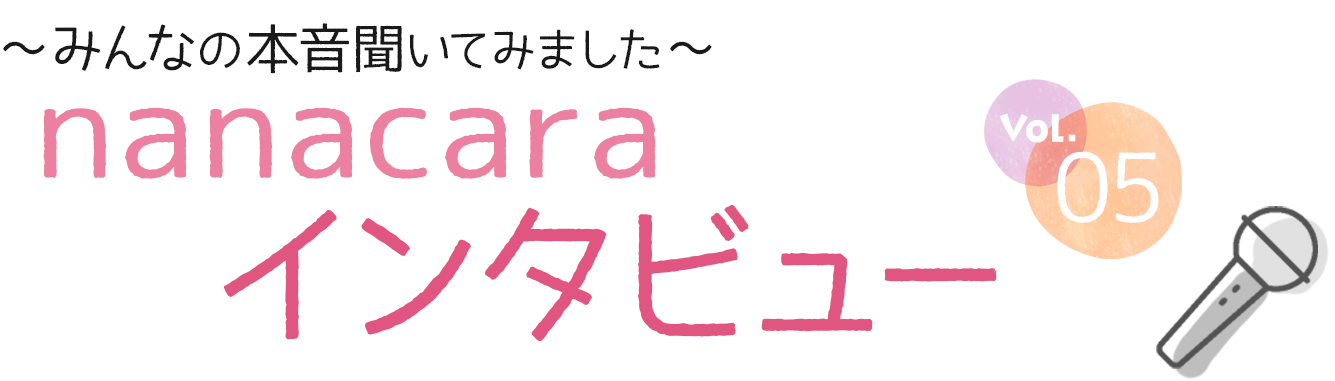
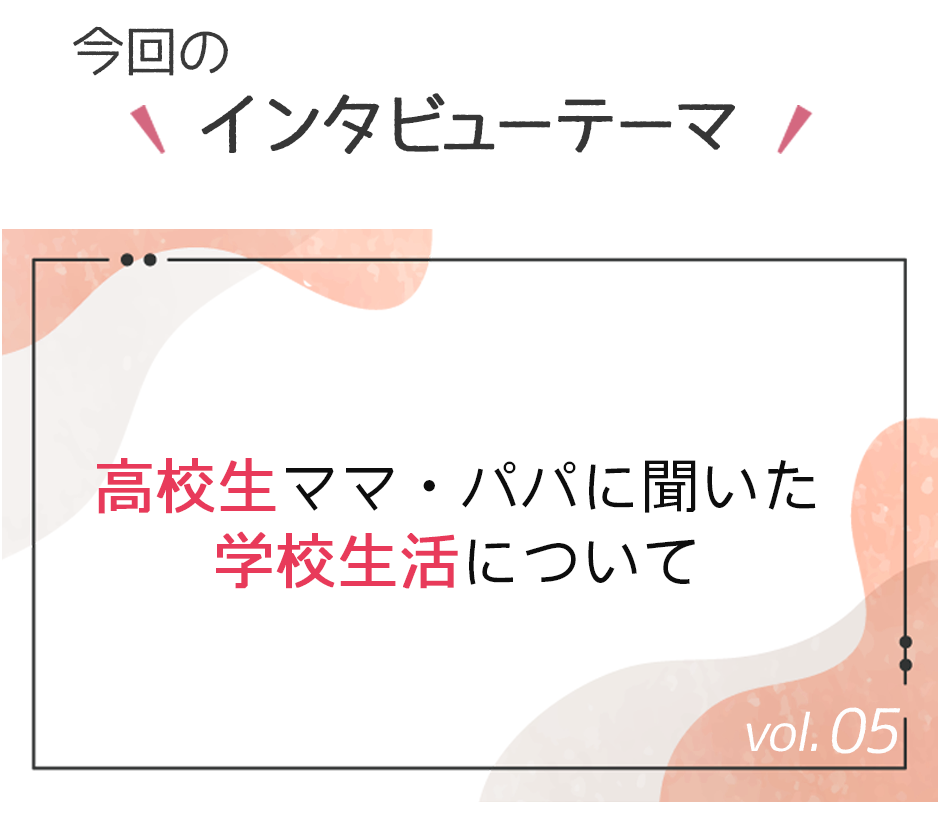
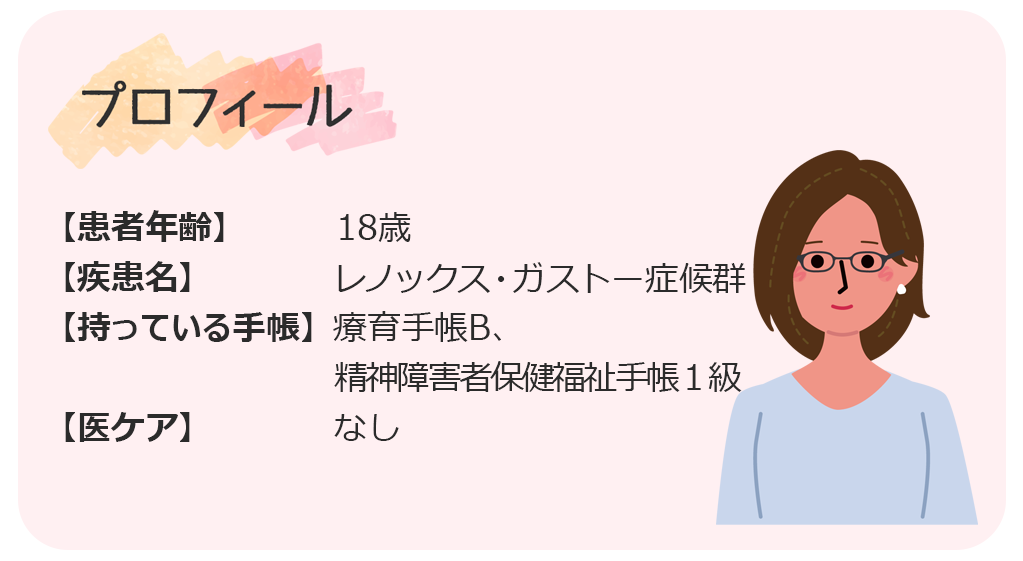
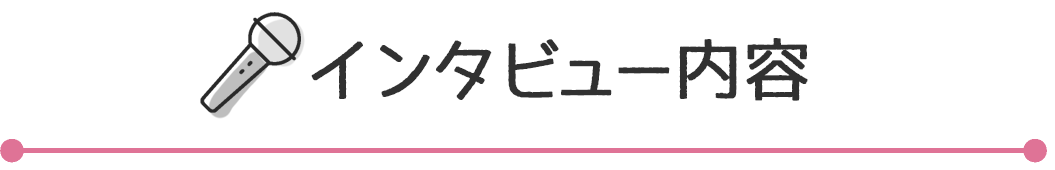
特にないですね。
振り返ってみても、今の選択でよかったと思っています。

小学校の頃から、できるだけ細かく連絡帳に書くようにしていました。中学校に進んでからも毎日欠かさず連絡帳を書いて、先生に伝えたいことを丁寧に記載していましたね。
高校でも同じように毎日連絡帳をつけていて、特に前日の夜からの様子や精神状態、発作や体調の変化など、細かいこともなるべく伝わるように心がけています。週明けには週末に何をしていたかも書いて、先生にできるだけ詳しく知ってもらえるようにしています。
...続きを読む
小学校を卒業する頃、ママ友から「もっと学校側に希望を伝えた方がいいよ」とアドバイスをもらいました。それをきっかけに、中学校の時には細かいことも学校にしっかり伝えるようにしていました。
高校1年のとき、ボーッとする発作があった際に先生から「指示が通るようになったら学校に来てください」と言われてしまったことがありました。その時は、発作の種類や状況を詳しく説明するように心がけ、今では先生たちにもとても理解してもらえるようになっています。
...続きを読む
現在、処方はされていません。

今は抗てんかん発作薬を3種類飲んでいますが、幸い副作用はほとんどありません。ただ、小学校5年生から中学1年生くらいまでは、副作用がかなりひどくて、暴れたり、しゃっくりが止まらなかったり、頭痛があったりしました。
ひどい時はすぐに医師に電話して薬をやめてもらったのですが、薬を飲まなくなってからもしばらく副作用が残ってしまって、特にイーケプラを飲んでいた頃のイライラが強くて大変でした。
その時期は、なるべく優しい口調で話しかけたり、褒めたり、一緒に遊んだりして、機嫌が悪くならないように気をつけていました。
...続きを読む

小学校では、プールや体育、運動会などには他の子と同じように参加していました。校外学習には母が付き添い、お泊まり学習や修学旅行では、夜だけ親と一緒に過ごす形をとりました。
中学校でも、プールや体育、運動会は通常通り取り組みました。修学旅行には先生から「大丈夫じゃない?」と声をかけられ、付き添いなしで参加しています。
高校に入ってからは、プール時には目立つよう帽子の色を変える工夫をして参加。体育や運動会も特別な配慮なく取り組めており、修学旅行でも付き添いはなしでした。旅行中に発作を起こす場面もありましたが、そのまま無事に全行程をこなすことができました。
...続きを読む

小学校は地域の学校の通常学級に通わせることにしました。入学前に先生にはてんかんのことを伝えていて、発作も少なかったので支援学校は検討していませんでした。
ところが、小学4年生くらいから発作が増え、担任の先生とのコミュニケーションがうまくいかず、息子も学校を休むことが増えました。その頃から自閉症の傾向も強くなってきて、小学5年生になると発作や遅刻が増え、引っ越しで通学班も変わったこともあり、学校に行きづらくなってしまいました。そこで小学6年生の時に、希望して特別支援学級へ移りました。
中学校は、家から歩いて行ける距離の地域の学校の特別支援学級を選びました。担当の先生が事前に話し合いで受け入れの姿勢を示してくださり、決めました。実は、母親としては外科手術をすれば発作が治るかもしれないという期待もありました。発作や行き渋りがあって休みがちでしたが、学校側から「給食だけ食べにきていいよ」「生徒が帰った後に保健室に顔を出しにおいで」など声をかけてもらい、とても嬉しかったです。
高校は特別支援学校を選びました。受験などは難しかったので、自宅から自分で通える距離の学校を選びました。入学に向けて通学の練習もしましたが、実際は送り迎えをしています。
譲れないポイントとしては、「自分で通えるかどうか」をよく考えました。
...続きを読む