



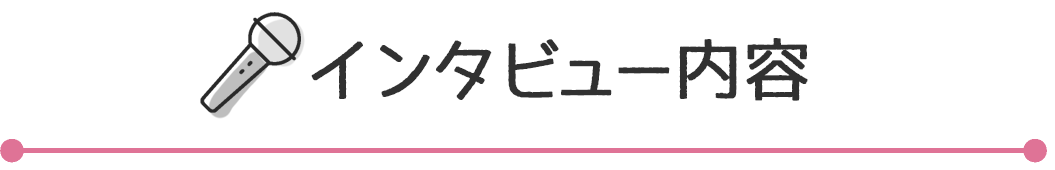
本当は、交流の面なども考えると、できれば4年生くらいまでは地域の学校の特別支援学級に通わせたかったんです。高学年になると学習面で難しくなってくるだろうとは思っていたので、はじめから6年間通うつもりでいたわけではありませんでした。
私自身、学童保育で支援員として働いていて、高学年の子たちの様子も日々見ていたので、「うちの子も高学年になったら地域の学校の特別支援学級で過ごすのは大変かもしれないな」と感じていたところもあります。
でも、実際はそれより早く発作が増えてきてしまって、通学そのものが難しくなってしまったんです。なので、3年生からは特別支援学校に転校せざるを得ませんでした。
...続きを読む
今振り返ると、地域の小学校へ入学する前に、私たち親だけでなく、本人ももっと一緒に学校へ連れて行っておけばよかったなと思います。何度か足を運んで、雰囲気に慣れておくことができたら、入学後もう少しすんなり場に馴染めたかもしれません。
でも、通っていた地域の学校では、周りの子たちがとてもよく関わってくれて、本当にありがたかったです。下の子が今年から同じ学校に通うのですが、「〇〇くんの弟だ!」って、みんなが声をかけてくれているみたいで、それも嬉しいですね。
ただ、地域の学校の特別支援学級は生徒がひとりだけだったので、教室でひとりで過ごす時間も多く、寂しい思いをさせてしまっていたかな、と感じることもあります。
...続きを読む

地域の学校の特別支援学級のとき(小学校1・2年生)は、毎朝送迎のときに直接先生とお話しして、その日の生活の様子や発作の回数、体調のことを伝え合っていました。それに加えて、紙の連絡帳も使って細かいことを書いてやり取りしていました。
特別支援学校に進んでから(小学校3年生以降)も、送迎時の対面での情報交換と紙の連絡帳は変わらず続けています。加えて、病院で薬が増えた時には、薬局でもらった説明書のコピーを先生に渡して、理解してもらうようにしています。
発作が短時間で収まったときは先生たちが様子を見てくれて、あとで報告してくれます。大きな発作があった場合は、電話で連絡をもらっています。
デイサービスでは、紙の連絡帳に加えてLINEでも連絡を取り合っていて、とても助かっています。
...続きを読む
地域の小学校の先生たちは、てんかんについて詳しく知らない方が多かったので、全ての先生に「こういう時はこう対応してください」とお願いしていました。お願いしたことはきちんと実行してもらえて、とても安心していました。
地域の小学校は、同じ敷地内に中学校もあるので地域の学校同士の交流の機会をもっと増やしてほしいなと思っています。
地域の人たちにも、てんかんなどの病気を持つ子どもがいることを知ってもらえると、理解も深まるのではないかと思います。
...続きを読む
緊急薬はダイアップを処方してもらっています。学校には預けていますが、これまで使ったことはありません。
地域の学校では緊急薬を使うことが難しかったのですが、特別支援学校では必要なときに使える環境が整っているので安心しています。

今は抗てんかん発作薬を2種類、朝と晩に飲んでいます。
副作用としては、食欲が落ちたり、吐き気があったり、眠気が強く出ることがありました。
学校には通えていたのですが、給食の時間の前に寝てしまうこともあって、その時は心配でしたね。

小学校の1、2年生のときは、プールにも参加していました。
運動会にも参加したのですが、2年生のときはみんなと一緒に列に並ぶのが少し難しかったようです。
その後、特別支援学校に進んでからは、地域の小中学校と合同の運動会に参加しています。
お泊まりの行事については、今の状況だと付き添いが必要かもしれないと言われています。
...続きを読む

幼稚園に入るときは、診断名やてんかんのことも全部伝えたうえで入園しました。地方の小さな園だったこともあって、先生たちの中にはもともと顔見知りの方もいて、すんなり受け入れてもらえたのはありがたかったです。
その後、幼稚園に通いながら療育園にも週に2〜3回通うようになりました。両方の良いところを活かして過ごしていたと思います。
小学校に上がるときには、ちょうど家の近くに特別支援学校の分校が新しくできたのですが、生徒数も少なくて見学ができなかったんです。それに、地域の特性として、ほとんどの子が地域の学校の特別支援学級に進学するということもあって、小学校の特別支援学級の先生たちは、障がいのある子どもたちへの対応に慣れていたように思います。
何より、幼稚園の仲間と一緒の小学校に行きたいという気持ちが本人にも私たちにもあったので、就学前の相談では特別支援学校をすすめられたものの、希望をしっかり伝えて、地域の学校の特別支援学級に通えるように受け入れ体制を整えてもらいました。毎朝、私が送り届けていました。
でも、小学2年生ごろから発作の回数が増えて、日中に寝てしまうことも多くなってきました。通院の頻度も上がって、学校にいられる時間が短くなっていきましたし、養護教諭の先生がずっとついていてくれるわけでもないので、次第に通学が難しくなってきたんです。学校の先生もどこか不安そうな表情をされていて、こちらとしても医療的な不安がどんどん大きくなって…
学校で発作が増えてからは、お友だちに手が出てしまったり、突然道路に飛び出してしまったりと、行動面にも影響が見られるようになって。そういった経緯があって、小学3年生からは特別支援学校に転校することにしました。
中学校については、今と同じ特別支援学校に進むのか、それとも知的障がいがある子のための寄宿舎のある学校に行くのか、今まさに検討しているところです。最近は多動の傾向も見られてきて、家での見守りも少しずつ大変になってきたなと感じています。
...続きを読む