
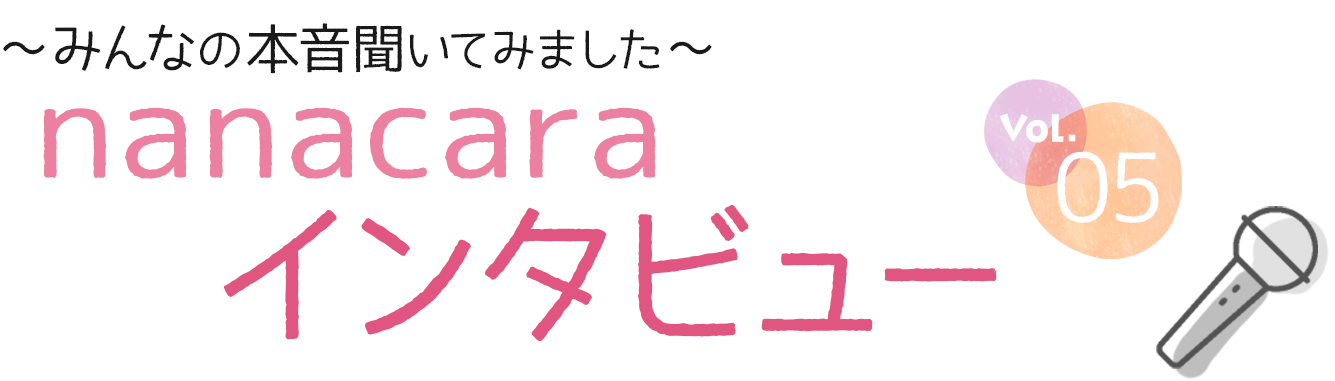
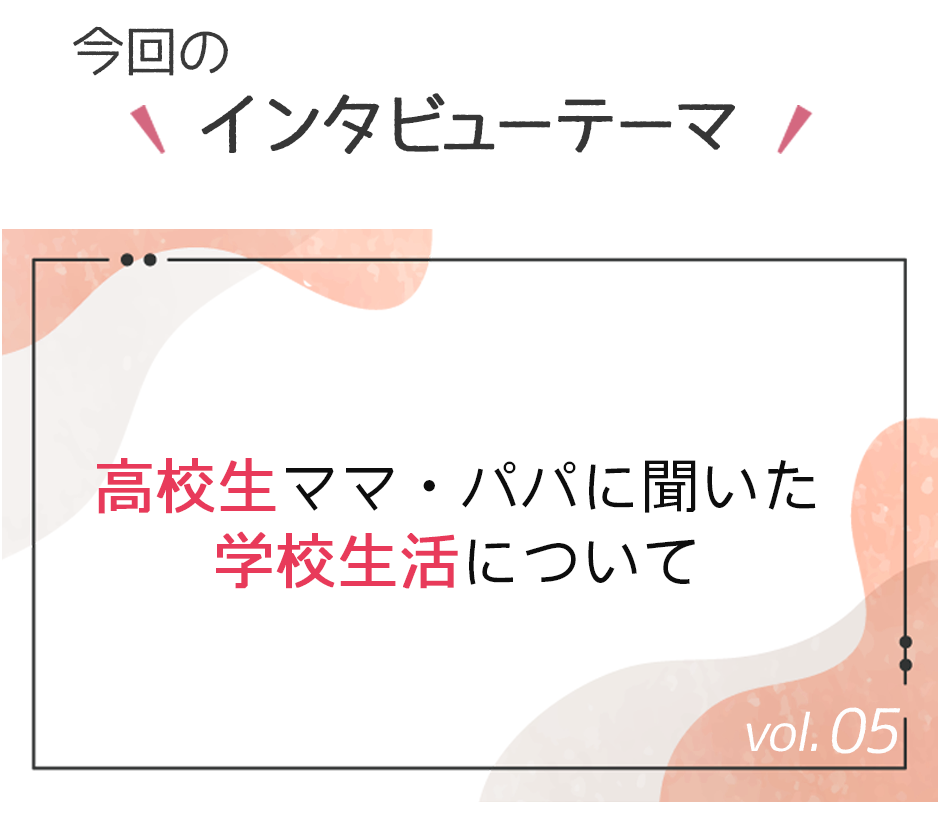
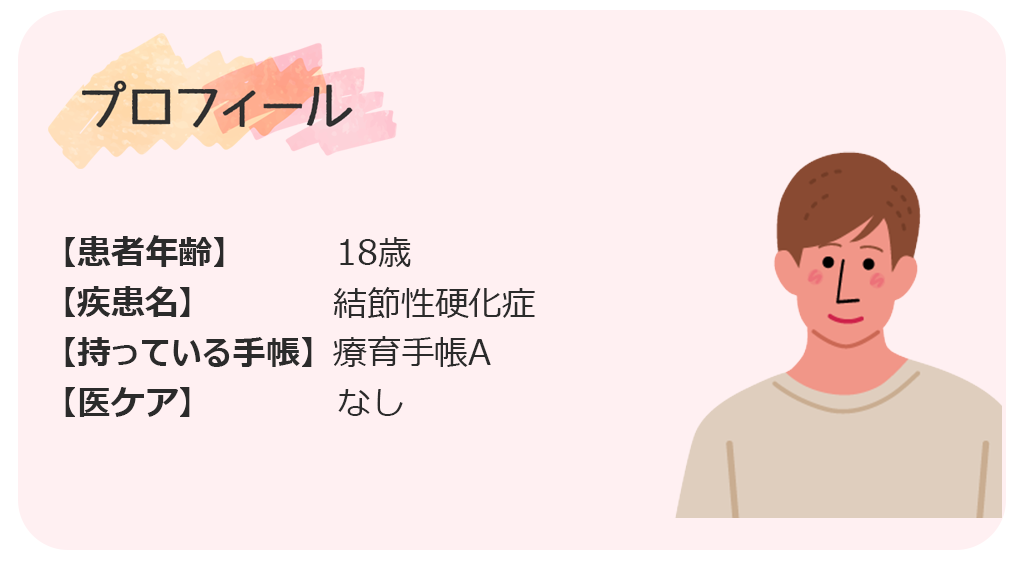
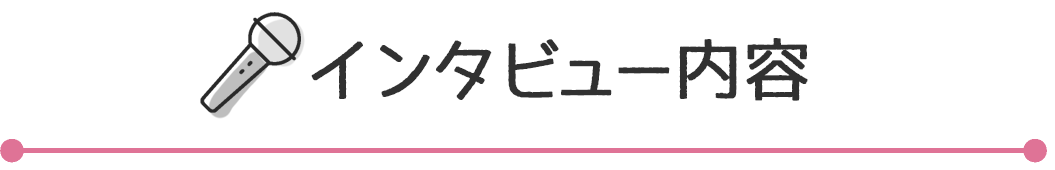
小学校に入る前、支援学校も見学していて、「ここに行けば、息子に合った療育を受けられて、自立に向けた支援も手厚いだろうな」と感じていました。
正直、そういう面では支援学校を選ぶべきかもしれないという気持ちもあったんです。
でも最終的には、地域の学校を選びました。
やっぱり、友達と一緒に過ごす時間、その経験には何ものにも代えがたい価値があると思ったからです。
その時間を息子にも持たせてあげたかったんです。
中学校では、入ってから「作業メインのカリキュラム」だということを知りました。
小学校のときのような学習中心の授業ではないことを、その時に初めて知って、少し驚きました。
小学校在学中に、支援学校小学部の同級生たちと月1回の交流の機会を作っていたので、中学から支援学校に進んだときも、すでに友達がいて、最初からクラスになじむことはできたんです。
でも、その分、授業の内容までは事前にきちんと把握できていなかったな、というのは振り返って思うところです。
支援学級は「学習メイン」で、障害の程度が軽い子が多く、友達との交流の時間もたっぷりあります。
一方で、支援学校は、「日常生活を一人でできるようになる」ための学びが中心です。たとえば、洋服の着替えやトイレの意思表示など。
その違いをもっと早く、深く理解できていたら、また違った準備の仕方もできたかもしれませんね。
...続きを読む
「もっとこうしたらよかった」と思うことですね。きっと、あるにはあると思うんです。
でもそれを口に出してしまうと、まるで息子のこれまでを否定してしまうような気がして、それはしたくないなと思っています。
親として、これまでの選択はその時その時で「これが一番いい」と思って選んできました。
だから後悔ではなく、自分たちなりのベストを尽くしてきた、そう思っています。
...続きを読む

小学校のときは、朝と帰りの送り迎えのタイミングで直接先生と話をしていました。
連絡帳は使っていませんでした。
発作があったときは学校から電話がかかってきて、迎えに行くという形でした。
中学校・高校でも、発作の関係でスクールバスを使えないため、毎日送迎しています。
そのときに先生と話す機会を持っていますし、担任の先生とはLINEも交換していて、発作の様子や学校での様子を連絡してもらっています。
毎日の連絡は紙の連絡帳に書いています。
連絡帳には、睡眠時間や排便の状況、朝食の状態など、細かいことも記録して先生に伝えるようにしています。
...続きを読む
特別支援学校に進んだら、きっと熱意のある先生ばかりで、特別支援に思い入れが強い方が多いと思っていました。
でも実際は、そうでもないと感じることがあり、あまり多くを求めないようになってきました。
学校に送っていくときに見える先生たちの様子から、そんな印象を持つことがありました。
小学校の特別支援学級の先生は、ベテランの方が多かったのですが、私たちが求めることと先生のやり方が合わないこともよくありました。
ただ、先生も豊富な経験をお持ちなので、そこは仕方がないかなと思っています。
...続きを読む
小学校のときは、ダイアップを学校に預けていましたが、発作が起きると学校から電話がかかってきて、私が保健室に行って使っていました。
中学校・高校になると、看護師さんが常駐しているので、学校の方でダイアップを使用してくれています。
今年の4月はダイアップの使用頻度が高かったのですが、あまり発作が止まらなかったため、その後ブコラムに切り替えました。
ブコラムについては、練習キットを取り寄せて学校で説明会も開きましたが、まだ学校では使われていません。
...続きを読む

今、息子は抗てんかん発作薬を5種類と、興奮を抑える薬を服用しています。
副作用のひとつに口内炎があり、疲れていると特に出やすいです。
その時は、歯磨き粉の量を減らしたり、ヘッドの小さい歯ブラシを使ったりしてケアしています。
口内炎ができているときは、卵かけご飯のように口当たりの良いものを食べることが多いですね。
...続きを読む

小学校のときは、プールの時間に私が付き添っていました。
高学年になると体も大きくなったので、一緒にプールに入ることもありました。
行事には1年生の頃から私も参加していたので、周りの生徒たちも私の存在に慣れていました。
一緒にいることで、息子と他の子どもたちの関わりを間近に見ることができ、良い機会になっていました。
修学旅行にも私が付き添いで同行しました。
運動会では、応援席の脇で私が待機して息子の様子を見守り、マラソン大会では伴走もしていました。
中学・高校の修学旅行では、発作が多い時期だったため、やはり私が付き添いました。
...続きを読む

診断を受けたとき、私は仕事を辞めて息子のサポートにまわることにしました。
保育園は、私が働いていなかったことや、これまでに指定難病の子を受け入れたことがなかったことから、最初は入園を断られていました。
でも、上の子の送り迎えで息子も一緒に通っていたときに、その様子を見てくださった所長先生が、最後の1年だけ声をかけてくださり、入園が実現しました。
小学校は、入学する年の2月下旬まで決まらなかったのですが、最終的には「何かあったときに保護者が付き添うのであれば」という条件で、地域の学校に通えることになりました。
登下校は私が毎日付き添い、支援学級の先生が出張やお休みの日には、息子も早退やお休みをしていました。
朝の会や帰りの会、クラス活動、音楽や体育の時間などは、通常学級で過ごしていました。
「障がいがあっても、そのときにしか体験できないことを経験させたい」そんな思いがあり、地域の学校を選びました。
そして、小学6年生のときには、私から学校へ働きかけて、月に1回、特別支援学校との交流の機会を設けてもらいました。
中学校については、小学校に入学する時点で「6年間は地域の学校で学び、その後は支援学校へ進む」と決めていました。
障がいの状態を考えると、中学からはより専門的な支援が必要だと判断し、自立に向けたサポートが受けられる支援学校を選びました。
...続きを読む