
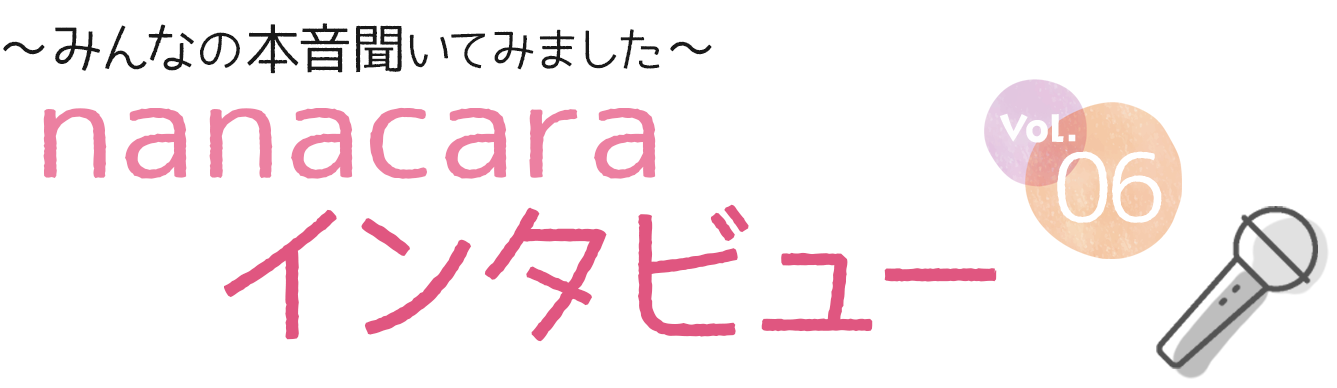
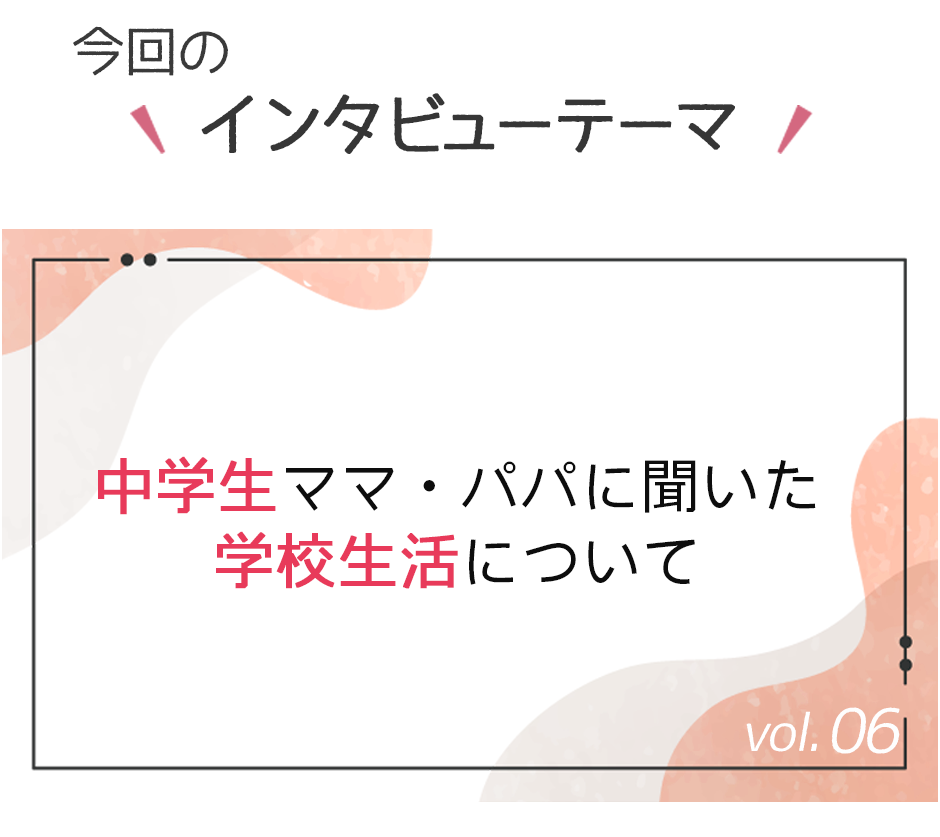
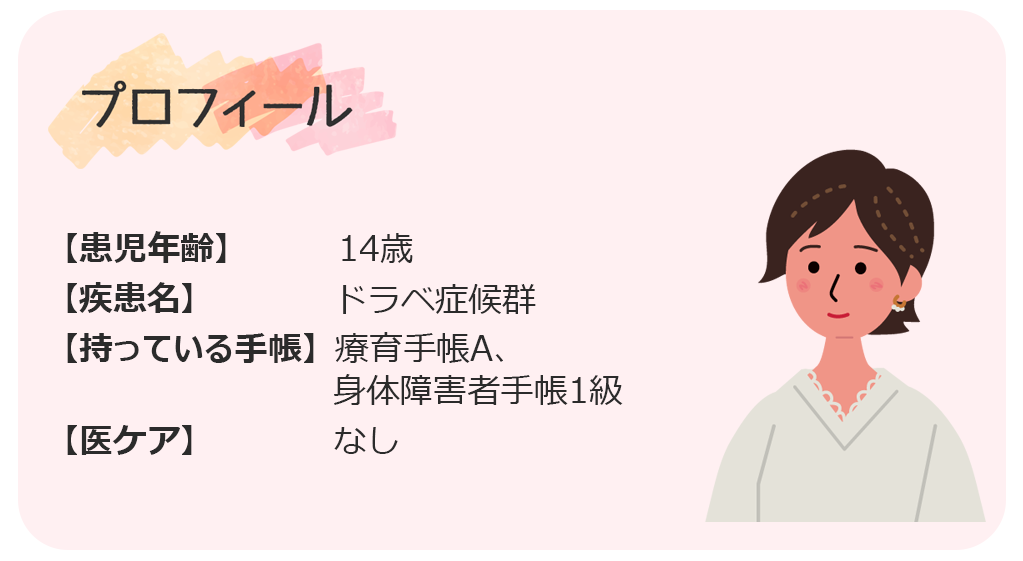
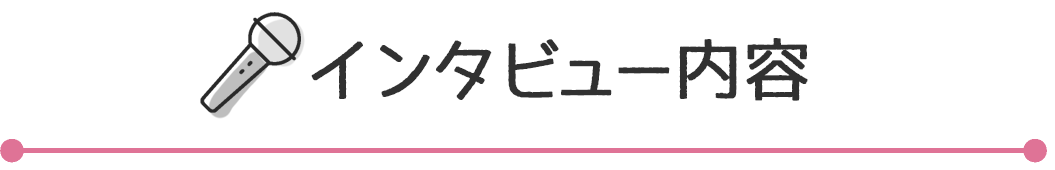
学校選びについては、もともと選択肢がひとつだったので、「これを諦めた」というようなことは特にありませんでした。
ただ、学校生活の中でひとつ難しさを感じたのは、ダイアップの使い方についてです。
ドラべ症候群の子どもは、予防的にダイアップを使いながら生活することがよくあるのですが、
学校では「ダイアップを使った=体調が悪い」と判断されてしまい、すぐにお迎えの連絡がくることがありました。
主治医の先生が丁寧に資料を作って説明してくださったのですが、学校側にはなかなか理解してもらえませんでした。
...続きを読む
もし、もう少し発作が落ち着いていたら、地域の学校を選ぶことも考えたかもしれません。
居住地交流のときに出会った地域の学校の男の子が、街で娘のことを見かけたときに声をかけてくれたことがありました。
娘はよく自宅の前で大きな声を出してしまうのですが、それを見ていた地域の女の子が少し冷たい目で見ていたとき、その男の子が「この子はこういう病気なんだよ」と説明してくれていたんです。
その様子を見て、将来のことを考えても、地域の子どもたちに「知ってもらう」ということはとても大きな意味があるんだな、と感じました。
...続きを読む

学校では毎日、紙の連絡帳を使っています。
家での様子や学校で覚えた言葉などについて私から先生へ質問することもあります。
デイサービスにも連絡帳はありますが、忙しいこともありあまり書かれていません。私は体調や生理のことを書いています。
療育園のときは、毎日2ページほどびっしり書かれていました。
中学1年生からはスクールバスで通っています。
小学校のときは発作が多かったことや、感染症にすぐかかってしまうのが心配で、私が送迎していました。
...続きを読む
学校の先生には、発作が起きたときの対応や、発作を起こさないための配慮をしっかり理解してほしいと伝えています。
特に4月や6月は体温調節が難しい季節なので、その時期は特に気をつけてくださいとお願いしています。
学年が変わるたびに、新しい担任の先生には口頭でそのことを伝えています。
緊急薬は、ブコラムとダイアップの2種類が処方されています。
学校にはブコラムを預けていますが、ダイアップを使った場合はお迎えが必要になるため、学校には預けていません。

今は抗てんかん発作薬を5種類、朝晩に分けて飲んでいます。
フィンテプラという薬を使い始めたときに、副作用でふらつきが強く出てしまい、歩けなくなるほどでした。
今でも少し歩行が不安定な状態が続いています。

プールの授業は、小学2年生までは発作が多かったため参加していませんでした。
3年生になって初めてプールに入り、その初日は付き添いで見守っていました。
4年生のときはコロナの影響でプールは中止に。
中学1年からプールは再開したのですが、
中学2年からはある事情で先生を信用できなくなり、プールはやめてシャボン玉遊びを楽しんでいます。
体育祭は毎年参加していて、5月の暑さに配慮してクールダウンには気をつけています。
遠足は、小学2年生までは近くで見守っていましたが、3年生ごろからは学校にお任せするようになりました。呼び出されることはありませんでした。
小学6年生の修学旅行には母も付き添いました。
今年度の宿泊学習では寝る時間を守ってもらえなかったのが少し気になっています。
...続きを読む

最初は、病院内にある療育園に通っていました。
静岡にある病院を受診した際に「療育が必要」と言われて、発作のときすぐに搬送できるように、病院の中にある療育園を選んだんです。
ただ、そこは医療的ケアが必要なお子さんが中心の園だったので、うちの子には少し合わなくなってしまって…。
そんなときに、自宅近くの障害者スポーツセンターで歩く練習をしていたら、偶然、療育園の園長先生とお会いして、「うちにおいで」と声をかけてもらって、そこから4年間通わせていただきました。
小学校のときは、発作が多かったので地域の学校は難しいかなと感じていました。
地域の学校の校長先生と面談をした際、娘も一緒に行ったんですが、その時の対応があまり優しいものではなくて…。
一方で、特別支援学校の校長先生はとても親身になって話を聞いてくださって、安心してお願いできると思いました。
中学校も小学校と同じ特別支援学校に進みました。
就学の際に譲れないと思っていたのは、「発作が起きたときにきちんと対応してもらえるかどうか」ということです。
救急車を迷わず呼んでくれる学校かどうか、それが何よりも大事でした。迷ってしまうと命に関わるので…。
...続きを読む